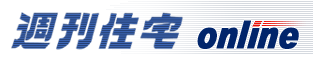|
【質問】
マクロ経済学において、総供給Y(S)=C+Sで定義されています。先生の入門書に記載の通り「消費された分+消費されなかた分」との記載があり理解できますが、消費されなかった分は、生産者の在庫として残り、これが貯蓄(S)になるとイメージできません。
何故、在庫=貯蓄なのでしょうか?また、私の考え方は間違っているでしょうか?(2010年1月) |
【回答】
まず、ご質問にあった、在庫=貯蓄は誤りです。
貯蓄(S)は、受け取った所得のうち消費されなかった分であり、この分は金融機関などにあり、やがて融資を受けたい企業などに貸し出され、それが投資(I)になるでしょう。
つまり、消費(C)された分はそのまま経済を大きくさせますが、残りの消費されなかった分の貯蓄(S)はこれから経済を大きくさせる余力を表わしています。そしてそれが投資(I)に回ると、その分だけまた経済が大きくなりますが、それ以上は大きくならないので、貯蓄=投資の状態が経済が均衡したと言います。
一方、在庫というのは投資の一種です。よく在庫投資という言葉でも説明させます。
在庫投資は短期投資で、長期投資には設備投資があります。
企業が、金融機関から融資を受けてそれを在庫投資に利用する場合もあります。
まとめると、貯蓄(S)は供給サイドの話(総供給=消費+貯蓄)で在庫投資(I)は需要サイドの話(総需要=消費+投資)ですので区別しなければなりません。
どうぞがんばってください。ご健闘をお祈りします。 |