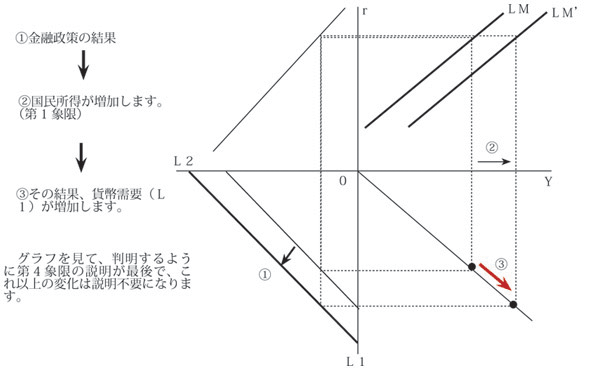
幙栤帠崁乮庴尡惗乯
傜偔傜偔儅僋儘宱嵪妛擖栧偺p140偵丄係徾尷傪巊偭偨LM嬋慄僔僼僩偺愢柧偺僌儔僼偑偁傝傑偡丅
偦傟偵偮偄偰偳偆偟偰傕傢偐傜偢丄嫵偊傪岊偊側偄偐偲巚偄丄埲壓彂偒崬傒偝偣偰捀偒傑偟偨丅
嘆p140偵傛傞偲嬥梈娚榓惌嶔傪幚巤偡傞偲丄M/P=L1+L2丂偺M偑憹戝偡傞偺偱丄LM嬋慄偼塃僔僼僩偟傑偡丅
嘇嘆偲偼応柺偑堎側傝傑偡偑丄壿暭廀梫偑憹戝偡傞偲偒偼丄棙巕棪偑忋偑傝搳帒偑尭彮偟丄崙柉強摼偼彫偝偔側傞偺偱丄LM嬋慄偼嵍僔僼僩偡傞偲巚偄傑偡丅
嘆偲嘇偺寢榑偼惓偟偄偲巚偄傑偡丅
偱偡偑嘆偲嘇偺働乕僗偵偮偄偰惍崌揑偵帺暘偺拞偱棟夝偱偒傑偣傫丅
側偤偐偲偄偆偲丄嘇偵偍偄偰丄壿暭廀梫偑憹戝偲偼M/P=L1+L2丂偺塃曈偺壿暭廀梫L偑憹戝偡傞偲巚偆偺偱偡丅偡傞偲丄嵍曈偺M偑憹戝乮枖偼P壓棊乯偡傞偲巚偄傑偡丅
偲偄偆偙偲偼丄嘆偲摨偠儊僇僯僘儉偱丄LM偼塃僔僼僩偡傞寢壥偵側偭偰偟傑偟傑偡丅偙偙偼丄LM偼嵍僔僼僩偡傞寢榑偲側傞偼偢偲巚偄傑偡丅
嘇偺峫偊曽偼丄偳偙偑娫堘偭偰傑偡偱偟傚偆偐丠
偱偒偨傜丄嫵偊偰偔偩偝偄丅
-------------------------------------------------------------
夞摎乮栁栘乯
崙柉強摼偑憹壛偡傞寢壥丄壿暭廀梫乮L1乯偑憹壛偡傞偺偱偁偭偰丄偦偙偐傜偝傜偵LM嬋慄傪僔僼僩偝偣傞傛偆側偙偲偼偍偒傑偣傫丅乮僌儔僼偵塭嬁傪梌偊傑偣傫丅乯
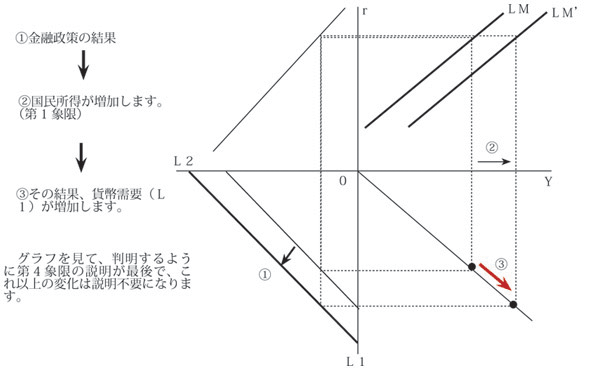
-------------------------------------------------------------
夞摎亅俀丂乮栁栘乯
> 偱偡偑嘆偲嘇偺働乕僗偵偮偄偰惍崌揑偵帺暘偺拞偱棟夝偱偒傑偣傫丅
> 側偤偐偲偄偆偲丄嘇偵偍偄偰丄壿暭廀梫偑憹戝偲偼M/P=L1+L2丂偺塃曈偺壿暭廀梫L偑憹戝偡傞偲巚偆偺偱偡丅偡傞偲丄嵍曈偺M偑憹戝乮枖偼P壓棊乯偡傞偲巚偄傑偡丅
> 偲偄偆偙偲偼丄嘆偲摨偠儊僇僯僘儉偱丄LM偼塃僔僼僩偡傞寢壥偵側偭偰偟傑偟傑偡丅偙偙偼丄LM偼嵍僔僼僩偡傞寢榑偲側傞偼偢偲巚偄傑偡丅
L1傑偨偼丄L2偑曄壔傪偡傞偲LM嬋慄偼僔僼僩偟傑偡偑丄M/P偼掕悢偺傑傑乮僌儔僼忋傪堏摦偡傞偩偗偱僔僼僩偼偟傑偣傫丅乯偱偡丅
偮傑傝丄壿暭廀梫偑憹壛偟偰LM嬋慄偑僔僼僩偟偰傕丄M/P偺戞俁徾尷偺僌儔僼偼曄壔偟側偄偨傔偵丄2師揑側LM嬋慄偺堏摦偼峫偊傑偣傫丅
-------------------------------------------------------------
擺摼丂乮庴尡惗乯
巹偑姩堘偄偟偨尨場偼師偺撪梕偱偡丅
偍栶偵棫偮傛偆偱偟偨傜偲巚偄丄偒偪傫偲彂偙偆偲巚偄傑偟偨丅
宱嵪偺夁嫀栤乮H俋偺搚抧偺帒嶻壙抣偺塭嬁偵娭偡傞栤戣乯傪
傗偭偰傑偟偰丄偦偺夝摎偺拞偵師偺婰弎偑偁傝傑偟偨丅
>搚抧壙奿偺忋徃偵傛傞帒嶻岠壥偵傛傝丄壿暭廀梫偑憹壛偡傞
偙偲偵傛偭偰丄LM嬋慄偼嵍僔僼僩偡傞丅
巹偼丄偙偙偱壿暭廀梫偲彂偄偰偁傞傕偺偩偐傜丄偙偺壿暭廀梫
偼L1亄L2傪巜偟偰傞偺偩偲巚偄傑偟偨丅
偦偟偰丄壿暭廀梫偺憹壛偼L1亄L2偺憹壛偩偐傜丄偮傑傝M/P偺
憹壛偵側傞偲巚偄傑偟偨丅
偦偙偱丄M/P偺憹壛偼嬥梈惌嶔偩偲巚偄丄偙偙偱惍崌惈偑側偄
偲巚偭偰偟傑偄傑偟偨丒丒丒
偙傟偑丄媈栤偺敪抂偱偟偨丅
偱傕丄傜偔傜偔傪撉傓偲帒嶻岠壥偵偍偗傞壿暭廀梫偼丄L2側傫
偩偲傢偐傝傑偟偨丅
宱嵪偼摎偊傪撉傓偲娙扨偵彂偄偰偁偭偰丄傢偐偭偨傛偆側婥偵
側傝傑偡偑丄幚嵺偵帺暘偺摢傪巊偆帪偵偼丄偁傟丠偭偲側傞偙
偲偑懡偄偱偡丅
崱屻傕婃挘傝傑偡丅偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨丅